
飲食店が海外進出するには?海外展開のメリットと開業の流れ・補助金
目次[非表示]
- 1.日本の飲食店の海外進出は増えている?
- 2.日本の飲食店が海外進出するメリット
- 2.1.日本食人気の高まりによる需要が見込める
- 2.2.販路の拡大と経営リスクの分散を図れる
- 2.3.コストを抑えられれば利益を増やせる
- 2.4.国内でのブランドイメージが向上する
- 2.5.新メニューの開発に海外の文化を導入できる
- 3.日本の飲食店が海外進出する方法
- 3.1.STEP1:事前に情報収集する
- 3.2.STEP2:事業計画を立てる
- 3.3.STEP3:必要な資金を調達する
- 3.4.STEP4:店舗物件を選ぶ
- 3.5.STEP5:お店作りと開業手続きを進める
- 4.日本の飲食店が海外進出する際の課題・注意点
- 4.1.現地の法規制や商慣習を把握する
- 4.2.食文化や味の傾向を理解する
- 4.3.現地での人材確保・教育が必要になる
- 4.4.日本から食材を輸入できない場合がある
- 5.飲食店の海外進出をサポートする補助金
- 5.1.事業再構築補助金
- 5.2.小規模事業者持続化補助金
- 5.3.海外展開・事業再編資金
- 6.まとめ
日本の飲食店の海外進出は増えている?

農林水産省の調査によると、海外における日本食レストランの数は増加傾向にあります。2006年には約24,000店だった出店数が、2017年はおよそ5倍の約11万8,000店に、2023年は約18,7000店になりました。増加率は地域によって異なりますが、特にアジア諸国や中東、中南米などでは、2015年から2017年にかけて大幅に増加しています。
海外で日本食レストランの店舗数が増えた理由としては、海外で日本食ブームが起きたことが挙げられます。海外では日本のアニメなどの影響から日本食への興味・関心が高まり、チェーン店も多く進出するようになりました。また、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されたことも、日本食が世界で広く認知されるようになったきっかけの1つです。
外食産業の国内市場は、2020年から2021年にかけてコロナ禍の影響を受けて落ち込みましたが、2024年時点ではコロナ前の水準に戻りつつあります。しかし、2025年以降の国内の市場規模は成長が鈍化する可能性が指摘されているため、今後ビジネスの拡大を図るには海外進出を視野に入れる必要があると言えるでしょう。
(出典:農林水産省「和食に対する世界からの注目」/https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/wasyoku_unesco5/data.html)
(出典:農林水産省「海外における日本食レストラン数の調査結果(令和5年)の公表について」/https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/231013_12.html)
(出典:富士経済グループ「イートインやインバウンド需要を取り込む外食産業市場を調査」/https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24060&la=ja)
日本の飲食店が海外進出するメリット
日本の飲食店の海外進出には、さまざまなメリットが期待できます。メリットを把握することで、より戦略的な事業展開につながるでしょう。ここでは、海外進出によるメリットを具体的に解説します。
日本食人気の高まりによる需要が見込める
日本食は世界的に人気が高まっており、海外でも需要が高い料理です。訪日外国人の中には、日本食を食べるのを楽しみにしている人や、好きな海外の料理として日本食を挙げる人が多くいます。
(出典:農林水産省「日本の「食文化」をめぐる情勢について」/https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaishoku_shokubunka/attach/pdf/index-332.pdf)
また、別の調査では訪日外国人が日本食を好きな理由としては「味が好みだから」が1位となっており、「食材が新鮮だから」「健康によいから」などが上位にランクインしています。
(出典:農林中央金庫「訪日外国人からみた日本の“食”に関する調査」/https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/uploads/2023/%E8%A8%AA%E6%97%A5%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%BF%E3%81%9F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E2%80%9C%E9%A3%9F%E2%80%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF%BC%BF.pdf)
ヘルシーな日本食は諸外国で人気の料理ジャンルであるため、海外進出の際は着実な来客が見込めるでしょう。
販路の拡大と経営リスクの分散を図れる
海外に進出すると、国内だけで展開するよりも客層を拡大して売上を増やせます。事業を1本に絞ると、主要な事業の業績が悪化したときに、企業全体の経営状態の悪化を食い止めるのが難しくなります。
しかし、事業拡大を行うことで経営の軸や販路を複数持てば、いずれかの事業の業績が悪化しても、企業の経営状態への影響は最小限で済む可能性が高くなります。飲食店が海外進出した場合、国内で業績が悪化しても、海外店舗の利益でカバーし、経営状態を健全に保つことが可能です。
コストを抑えられれば利益を増やせる
物価が安い国に出店する場合、食材の仕入れコストを抑えやすくなり、結果としてFLR比率を低下させる可能性があります。FLR比率とは、売上に対して食材費(Food)・人件費(Labor)・家賃(Rent)が占める割合を指す言葉です。FLR比率は飲食店における利益を分析する際に使われ、比率が低くなるほど利益は高く、比率が高くなるほど利益が低いと判断します。
飲食店が利益を上げるためにはFLR比率のコントロールが重要です。ただし、FLR比率を気にするあまりコスト削減に走りすぎると、サービスのクオリティが低下する恐れがあります。もともとその国の物価が安ければ無理なくコストダウンが図れるのが、海外進出ならではのメリットです。
国内でのブランドイメージが向上する
海外に出店し、「海外でも有名な企業」「世界でも注目されている」といった印象を持たれることで、国内でのブランドイメージが向上する場合があります。企業のブランドイメージは、消費者が特定の商品やサービスを選択する基準の1つです。いくらよいサービスを提供しても、数ある競合企業の中から自社の製品・サービスを選んでもらえなければ利益にはつながりません。
明確なブランドイメージを打ち出せると訴求力が高まり、より消費者の目に留まる確率が高くなります。海外進出によるブランディングが成功すれば、国内市場での激しい競争を戦い抜くための武器になるでしょう。
新メニューの開発に海外の文化を導入できる
競合他社が多い日本の飲食店では、いかに差別化を図るかが問われます。新規顧客の獲得に加え、リピーターを確保するためには、飽きられない魅力的なメニュー開発が必要です。
海外の出店先でのノウハウを生かせば、新メニューの開発に海外の文化を取り入れることも可能です。海外の食事や文化は、日本国内の顧客からは新鮮に感じられることが多く、新メニュー開発の下地に適しています。取り入れられる要素は出店した国によって異なるため、競合他社との差別化にもつながるでしょう。
日本の飲食店が海外進出する方法

海外での飲食店経営には国内と異なる点が多々あり、抜けや漏れがないよう進出の準備を慎重に進める必要があります。ここからは、日本の飲食店が海外進出するときの流れを解説します。
STEP1:事前に情報収集する
海外での出店に限らず、新たに事業を展開する場合は、事前に現地の情報収集が必要です。現地視察を行う前に、海外市場の動向や現地の飲食業界を取り巻く環境、競合店舗、現地の消費者のニーズ、トレンドなどを国内から調査しましょう。いずれの情報も古くなると価値が低くなるため、常に最新の情報をサーチすることが大切です。
情報収集の手段としては、書籍や新聞、SNSを含めたインターネットなど、さまざまな方法が考えられます。幅広く情報を集めたほうが調査の精度は上がるものの、手を広げすぎると調査に時間がかかります。事前にある程度調査の方向性を決めておき、調査対象を絞って効率化を図るのも1つの方法です。
STEP2:事業計画を立てる
情報収集の結果をもとに、事業計画を立てます。事業計画には、店舗のコンセプトや出店予定のエリア、資金計画などが含まれます。資金計画については、次の4つについて明確化しましょう。
- 投資計画
売上計画
損益計画
返済計画
食材などの売上原価や人件費、物件の家賃、設備投資費といった細かい分類もできる限り設定すると、計画の精度が高まります。また、資金計画には開業資金に加えて、運転資金・予備資金なども組み込み、余裕のある計画を立案することが重要です。事業計画に必要な情報を洗い出したら、事業計画書を作成します。
STEP3:必要な資金を調達する
事業計画書をもとに、海外進出に必要な資金を調達します。資金の調達方法は、主に次の3つです。
- 自己資金
知人や親族からの個人的な借り入れ
金融機関からの借り入れ
海外での開業には多額の資金が必要です。すべてを自己資金でまかなえないケースがほとんどのため、多くの場合は自己資金と借り入れを組み合わせて資金を調達します。借り入れを利用する場合も、ある程度自己資金を準備したほうが借り入れしやすくなります。
知人に借りる場合の金額は相手との関係や経済状況などによるものの、金融機関に借りる場合は3分の1から半額程度の自己資金を用意するとよいと言われています。
STEP4:店舗物件を選ぶ
資金調達に成功したら、新天地への出店にあたり店舗物件選びを行います。物件選びの際には、次のようなポイントを考慮しましょう。
- 家賃
店舗面積
物件周辺の人通り
近隣の交通機関やアクセス
建物の階数
すべての条件を満たす理想的な物件を見つけるのは簡単ではありません。可能な限り条件のよい物件を探すためには、店舗のコンセプトや予算に応じて、妥協できるポイントと譲れない条件を明確にしておく必要があります。
STEP5:お店作りと開業手続きを進める
お店作りは、店舗の設計からはじまり、内装・外装の施工や厨房の設備選び、食器の選定などを行います。お店作りには、事前に決めたコンセプトや事業計画を反映しましょう。開店の時期が決まったら、必要に応じて現地スタッフの募集も進めます。現地採用する場合は、現地での主な求人方法も調べておきましょう。
開業に必要な手続きは、進出する国によって異なります。進出先で必要な手続きについては事業計画の時点で洗い出しておき、届出に必要な条件を満たした上で準備を進めましょう。
日本の飲食店が海外進出する際の課題・注意点
日本の飲食店の海外進出には多くのメリットがある一方で、日本とは異なる文化圏に飛び込むことには課題も伴う点に注意が必要です。ここからは、日本の飲食店が海外進出するときの課題や注意点を、解決法を交えて説明します。
現地の法規制や商慣習を把握する
飲食店に関する法律には、営業許可や食品衛生、労働、税制に関するルールがあります。知らずに法律に違反すると、店舗のイメージを大きく損なう・営業を継続できなくなるといったトラブルを招く恐れがあります。
商習慣は、現地でスムーズに取引するために必要なルールやマナーです。日本のビジネスシーンで当然のように行われる行動が、海外では受け入れられないケースも多く見受けられます。たとえば、日本では決裁権を持たない営業担当者が商談に出ることが多い一方、海外で商談に対応するのは基本的に決裁権を持った人物です。また、商談前に名刺を交換しない場合が多く、「一度社内に持ち帰って検討します」という感覚もありません。
日本と海外では、飲食店の出店に関わる法律や商習慣が異なります。日本国内のビジネスの感覚をそのまま持ち込まず、現地の法規制や商習慣をしっかり把握しておきましょう。
食文化や味の傾向を理解する
現地の食文化や好まれる味の傾向などを調査し、理解を深めておきましょう。味の好みなどは国によってそれぞれです。日本食への興味が高まっているとはいえ、日本の味をそのまま現地に持ち込んでも受け入れてもらえるとは限りません。場合によっては、メニューに現地の食文化や味の好みを取り入れる必要があります。
ただし、メニューを現地化させすぎると、店舗独自のブランドイメージや魅力が失われる恐れがあります。店舗や日本食の独自性・魅力を生かせるように、現地の食文化や味をバランスよく取り入れる工夫が必要です。
出店エリアによっては、イスラム教における豚肉のように、宗教上特定の食材を口にできない人が多くを占めているケースがあります。出店エリアの状況に応じて、食材の置き換えや使用食材が分かるメニュー表示を行い、現地で受け入れてもらえるようにしましょう。
現地での人材確保・教育が必要になる
日本から現地への移住を伴う場合もあり、店舗スタッフを全員自社でまかなうのは現実的ではありません。場合によっては現地で人材を確保し、教育を行う必要があります。日本と海外では文化が違うため、日本でのやり方をそのまま採用・教育に取り入れるとうまくいかないケースが多く見られます。
株式会社力の源カンパニーの事例では、アメリカへの出店に際し、アメリカ人スタッフを雇用しました。アメリカでは仕事より家族を優先し、日本より労働者の権利が強い傾向があることから、日本と同じように勤怠管理が行えないという壁にぶつかりました。また、企業の保険負担額も大きく、よい人材を確保しにくいという問題にも直面しています。
インドネシアに進出した株式会社PrunZの事例でも、フロアスタッフとの英語での意思疎通を図れないことや、勤怠や休憩に対する感覚が違うことが問題でした。英語とインドネシア語の両方を話せるスタッフの採用、教育制度の構築により、コミュニケーションや勤怠関係の課題を解決しています。
このように、海外では採用も就業中の人材管理も日本のように進めるのは困難な場合があるため、現地のルールや状況を把握し、日本のやり方にこだわらずに対応する必要があります。
(出典:独立行政法人日本貿易振興機構「「海外サービス産業“課題・トラブル克服”事例」調査~当社は、こうして課題に対処した~」/https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/4d4f6ad8a418754a/rp_services_tr201509.pdf)
日本から食材を輸入できない場合がある
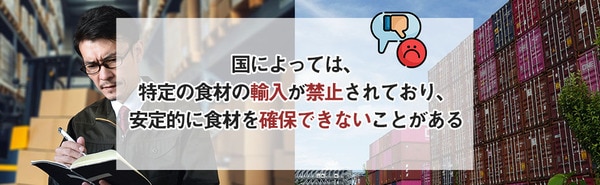
国によっては、特定の食材の輸入が禁止されており、安定的に食材を確保できないことがあります。安定して食材を確保できない場合、輸入禁止食材が使われているメニューは継続的に提供できません。
株式会社力の源カンパニーの事例では、震災後に米国食品医薬品局(FDA)によって一部の食材が輸入できなくなりました。代替品を使用したところ、商品の味が変わるケースが見られたため、輸入量を開業時より減らして現地調達するように対応しました。
マレーシアに進出した株式会社フリースタイルの事例では、日本からの食材の輸入に想定以上の税金がかかり、規制も多い状況でした。しかし、サプライヤーが飛び込みで営業に来たことをきっかけに、食品以外は現地で補うようにしています。
安易に食材を置き換えられない場合もありますが、可能であれば現地のほかの食材に置き換えるのも1つの方法です。
(出典:独立行政法人日本貿易振興機構「「海外サービス産業“課題・トラブル克服”事例」調査~当社は、こうして課題に対処した~」/https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/4d4f6ad8a418754a/rp_services_tr201509.pdf)
飲食店の海外進出をサポートする補助金
海外進出にあたっては、要件を満たすと補助金を受け取れる可能性があります。ここからは、飲食店の海外進出で受給できる可能性がある補助金について解説します。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、コロナ禍による需要や売上減少の影響を受けた事業者を対象に、事業再構築を支援するために設けられた制度です。認定経営革新等支援機関に事業計画書を提出して確認を受けるなどの条件を満たすと、補助金を申請できます。
成長分野進出枠の通常類型では、補助上限は3,000万円、補助率は3分の1から2分の1となっています。対象経費は、建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費・専門家経費、広告宣伝費・販売促進費、研修費などです。事業類型はそのほかのパターンもあるので、自社に合う条件の事業はあるか一度確認してみましょう。
(出典:事業再構築補助金/https://jigyou-saikouchiku.go.jp/)
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者を対象に、販路開拓や業務効率化にかかる経費を補助する制度です。補助を受けるには、各年度の受付期間中に審査書類を提出する必要があります。
通常枠では、補助上限は50万円、補助率は3分の2となっています。2024年時点ではすでに募集は締め切られていますが、今後新たな公募が可能となることも考えられるため、公式サイトなどで最新情報をチェックすることをおすすめします。
(出典:小規模事業者持続化補助金/https://s23.jizokukahojokin.info/index.php)
海外展開・事業再編資金
海外展開・事業再編資金は、日本政策金融公庫による融資制度で、海外で事業を開始・再編する中小企業者を対象としています。融資の対象経費は、事業のために必要な設備資金や長期運転資金です。
直接貸付は14億4,000万円、代理貸付は1億2,000万円を上限に融資を受けることができます。ただし、海外展開・事業再編資金は補助金ではなく融資制度のため、上限2.5%の利率が設定されています。条件を満たすと特別利率が適用され、金利が下がる場合があります。
(出典:日本政策金融公庫「海外展開・事業再編資金」/https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai_t.html)
まとめ
日本の飲食店が海外進出を成功させるためには、海外市場の特性を深く理解し、戦略的に準備を進める必要があります。法規制や食材調達の課題も伴うため、十分なリサーチと対策も欠かせません。現地の食文化や商慣習に適応しつつ、日本のブランド力を生かすことが成功の鍵です。
日本食の魅力を海外で伝えることは、新たな市場開拓のみならず、日本文化の普及にも寄与する意義ある挑戦です。補助金や融資制度も活用しながら、日本の食文化を世界に伝えましょう。



